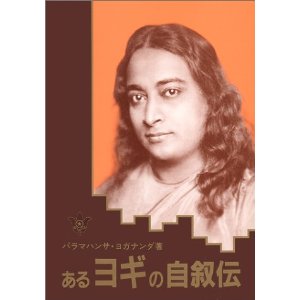自由というのは個人の心の問題でもあり、社会や世界の問題でもある。
インドが長らく求めてきた自由(解脱)は、太古には至って個人的な問題であった。そこに集団的要素を持ち込んだのは、かのブッダである。
ブッダは、それまで個々の修行者が世間を離れ山林独居しながら行なっていた苦行や修養に、弟子たちが集団となりサンガ(僧伽、集い)を形成して互いに切磋琢磨し良い刺激を与えながら行なう形態を導入した。このサンガ(僧伽)が、現在の「僧」の語源である。今ではそういった集団的修養は当たり前のようになっているが、ブッダの時代にはそうではなく、彼が起こした画期的な変化であった。
しかし目指すべき自由、悟りというものは、やはりあくまでも個人的な問題である。集団が同時に悟るというわけにはいかない。それにもかかわらず、ブッダがサンガという方式を導入したのには、非常に本質的で、今なお新しい洞察や直観が含まれているように思う。
現代になってますます大きな問題になっているのは、世界規模での気候変動や環境問題、そして国際的平和の実現やグローバル経済における好不況である。それらは全世界的な問題であると同時に、個人の心や一つの企業、一つの国の問題でもある。環境破壊は世界規模の問題でありながら、一人ひとりの心、考え方、生活の仕方が変わらなければ決して解決しないし、政治や経済の問題も一国だけで片付くものではない。むしろ一人ひとりの欲望や各国・各企業のエゴがそうした問題を引き起こしているといえる。
それに対して、私たちは未だに有効な解決法を見つけていない。だが、個人の問題が集団や世界の問題でもあるということを考えると、ブッダが導入した集団による目覚めへの道という画期的方法が、今なお新しい、未来への解決法を示してくれているようにも思えてくる。
それは、私たち一人ひとりが欲望から自由になることでしか世界の問題を解決することはできないということを意味するとともに、世界がサンガとして学ぶことによって個々の目覚めが起こりうるということを示している。つまり、個の目覚めとともにサンガ(集団)の目覚めもあり、それは現代的な文脈で言えば、世界としての目覚めもありうるということではないだろうか。
そこで大事なのは、集団が単なる個の集まりではなく、サンガでなければならないということだろう。互いの利害を理解して調整するという単なる横の関係ではなく、個々の深い本質と世界全体の深い本質が一つにつながったところから行動を起こす垂直的な関係。それが個のエゴを離れた自由であり、エゴを棄てた献身、世界・他者そして真の自己への奉仕になる。
私たちは一体何ができるのか? 物理的にも時間的にも私たちの肉体的・心理的存在は限られている。しかし、その個我を超えることができるならば、限定を超えた献身と奉仕が可能になるのではないか? そしてそれこそが真の自由ではないだろうか。ブッダは、弟子たちのほんの小さな集いを作った時から、そうした人間の本質を見抜いていたように思える。それがまた今、人類が一歩前に踏みだすための新しい意識と生き方としてメッセージを発しているように感じる。
サナータナ