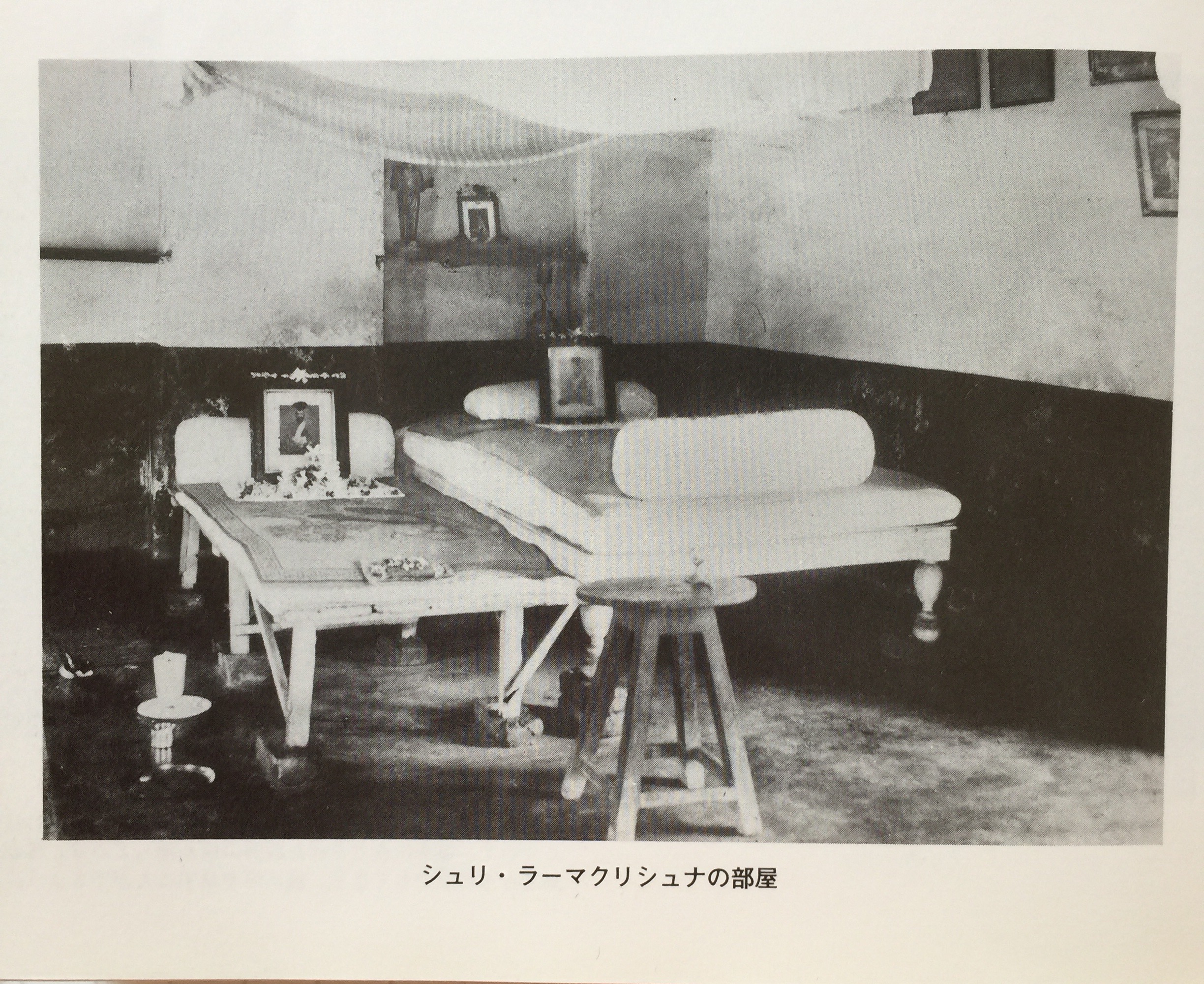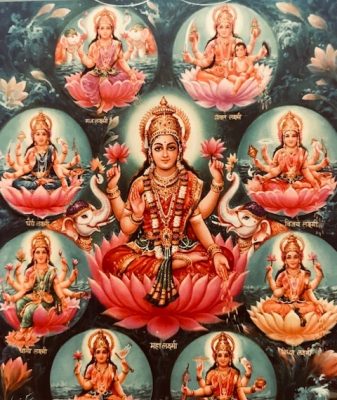ある時、師であるヨギさんがもっと神と一つになるようにと私におっしゃられたことがありました。神と一つになる、か・・・・・・と考えていた時、インドの大聖者シュリー・ラーマクシュナが弟子であるヴィヴェーカーナンダに授けた次のような教えが心に留まりました。
「愛のネクター(甘露)がビンの中に入っているとしたら、お前はどのように楽しもうと思うか」とおたずねになり、ナレーンドラは「私はネクターの入っているビンのふちに座って、そこから吸いましょう」と答えた。師は微笑され「なぜ中に入って吸わないのか。ビンの真ん中に入って吸えばよいではないか」とおっしゃった。「いいえ、そんなことをしたら死んでしまいます」シュリー・ラーマクリシュナは「そういうものではないのだよ。人は愛に溺れてもけっして死にはしない。それはアムリタ、不死そのものなのだから」と笑いながらおっしゃった。
ひとたびこの愛の味がわかると、魂にとってこれ以上ほしいものは何にもなくなる。この歓びは無限であり、何ものによっても増やすこともできなければ滅することもできない。
この教えに触れて、私の中で「神の愛に溺れたい!神と一つになりたい!」という思いが強くなっていき、しばらくは甘美なムードに浸っていたのですが・・・・・・。そのムードは小学校4年の娘が、夏休みに入るとともに消えていきました。
夏休みに入るといきなり、「学童に行きたくない!」と娘が泣き出したのです。事情を聴くと、仲の良い友だちが一緒に行ってくれなくなり、学童で一人ずっと過ごしているようでした・・・・・・。それからは家で一日どのように過ごさせるかや、お昼ご飯の準備などで頭の中はいっぱいになり、神よりも娘に集中する時間の方が多くなっていきました。娘と友だちの関係で気をもみ、一緒に遊ばせる段取りを組んだり、娘にこういうふうに考えたらどうかなとくどくど話したり、どうしてこんな簡単なことが理解できないのだろう・・・とイライラして感情的になったり、お世辞にも娘と調和がとれたようなものではありませんでした。
これではいけないと思って考えていると、娘が生まれた時、ヨギさんから「大らかに育ててください」と言われたことをふと思い出しました。私は自分の経験や価値観という小さな枠で彼女を見ている。物差しを当てず、常に自分を空っぽにする努力をして、彼女と向き合おうと思いました。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
そうして幾日が過ぎ、地蔵盆(※関西地域で行われる子どもたちの幸せと健康を願う行事)の日がやってきました。お布施をもって会場に行くと、先に行っていた娘が他の子どもたちと離れ、一人でポツンと寂しそうに遊んでいるのです。娘は私に気付くと(みんなで楽しく遊んでいるよ)と気遣って気丈に振る舞っているように見え、居たたまれない気持ちになりました。
その夜、娘の寝顔を見ながら、私は申し訳ない気持ちになって泣きながら謝っていました。この子の存在を自分は本当に尊んできたのだろうか、この子が友だちと楽しく過ごせるような環境を整える努力が、もっと必要だったのではないだろうか・・・・・・。・・・・・・でも・・・・・・友だちと仲良くなれるようにできるだけ努力をしてきたし、考えても、考えても、もう何をどうすればいいのか分かりませんでした。
シュリー・ラーマクリシュナの弟子であるトゥリヤーナンダは、『すべてのなやみを母(女神)のもとに持っていけ。彼女は一切の誤りを正して下さる、母を知れば、他の問題はなくなる。あなたが、自分を彼女に捧げ切ったとき、一切のものを新しい光の中で見るようになる。そして、この世の生活を問題にする必要のないことを知るのだ』と言われます。
もう神に祈るしかできない!という切羽詰まった思いで、ヨギさんとトゥリヤーナンダのお写真を前におき、瞑想に座りました。瞑想の後寝床についた時、突然聖なる力が私を押し上げ、ヨギさん、トゥリヤーナンダ、私、3つの意識が一つとなって、万物が展開していくビジョンが見えました。
意識が肉体に戻ったとき、すべては私が神から目をそらさないように神がなされていたんだ、と思いました。そして自分がすべきことは神だけを思うこと、という確信がありました。甘美なムードに浸るという漠然としたものではなく、日常としっかり向き合うことで神と一つになれるということが分かりました。
そして娘にとっての人生の目的もやはり、神と一つになること。友だちと楽しく過ごせるに越したことはないですが、友だちと一緒にいて安心することではないのです。親としてしっかりとそのことを踏まえ、関わっていきたいと思いました。
その出来事のあと、不思議と娘の状況はどんどん良くなっていきました。近所の子とまた自然に家を行き来するようになり、同級生が遊びに来たりするようになりました。また、他のお母さんたちと話すと少なからずどの子も同じようなことで悩んでいて、そういう多感な時期であることが分かりました。
こうして娘の夏休みは幕を閉じました。そして私の信仰をより強くしてくれたのでした。
 amara
amara