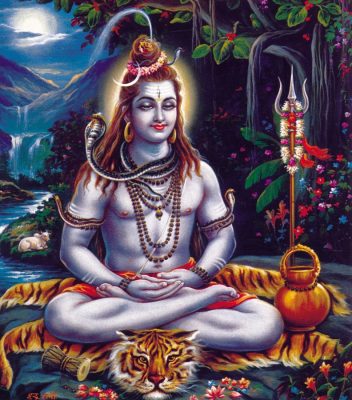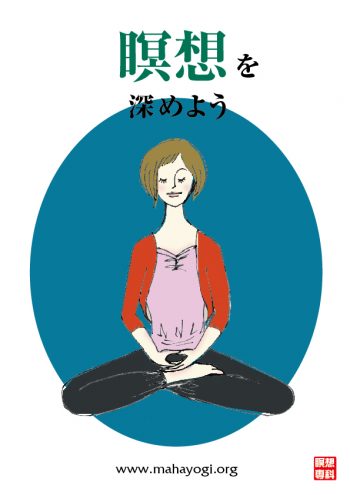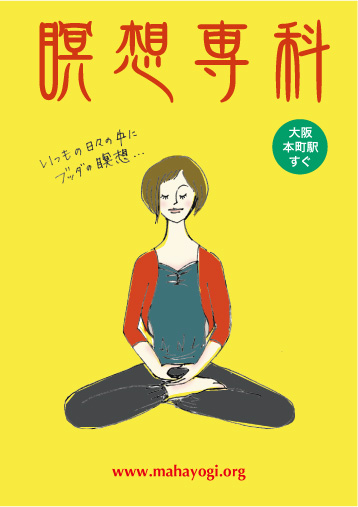京都ヨーガ・瞑想クラスの合同交流会がありました!
プログラムの初めにはアーサナのデモンストレーションがありました。今回はどのクラスでも人気もののゴパーラと土曜日のクラスに通い、最近とても熱心にヨーガと向き合っているMさんがアーサナをしてくれました。気迫に満ちたとても素晴らしいアーサナで、私自身は息を飲むような集中感にとても感動しました。
参加した皆さんも、食い入るようにデモンストレーションを見ておられました。「2人のアーサナを見て、集中間というものはこういうものかと感じた」「自分たちが普段しているアーサナの完成形が分かった」「いいものを見せてもらった」といった感想をいただきました。


その後、さまらさの食事を食べながら、自己紹介を兼ねて、皆さんがヨーガを始めたきっかけや、ヨーガをしてから変わったことなどを話していただきました。
クラスに通うようになって2年になる方が数人おられましたが、皆それぞれに2年前と比べて明らかな変化を感じておられるようでした。
ある方は数年ぶりに会った友人に「人相が良くなった!」と言われたようです。確かに最近の彼女は表情が明るく(昔が暗かったわけではないですが)とても軽やかな印象があります。
毎日アーサナをしていると言われた方は体にしっかりとした軸ができたと言われていました。確かに、最近の彼女からは芯の通った強さを感じます。
またある方は、仕事場でうまくいかなかった同僚と真理を学び瞑想していく中で怒りや不満の感情なく普通に話ができるようになったと言われていました。きっと瞑想によって心が変化し、動揺しなくなっていったからでしょう。
皆さんが日常生活の中で変化を感じながらクラスに通ってくださっていることを知り、とても嬉しかったです。
一方でアーサナの実践にムラがあり、甘いものがやめられない…と話されている方もおられました。それはそこにいる誰もが多かれ少なかれ経験があること、それぞれの体験を話しながら、みんなで自然とアドバイスしあいました。
みなさんの話を聞いていて感じたことは、調子が良い時も、悪い時もあり、状況は色々変わるし、誰もがトントン拍子でうまくいっているわけではないということ。人と比べる必要はなく、それぞれに道があり、コツコツと実践していくことで必ず進歩しているのだということです。
同じヨーガをしている仲間とこのようように話し、励まし、刺激しあえる機会はとても貴重だと思いました。
最後に話をしてくれたSさんは、熱心にクラスに通う中、自分の内に歓びがあることを体感し、自分自身も人に歓びを与えられる存在になりたいと話してくれました。彼女の話している言葉や姿、発しているプラーナ(気)から歓びが溢れ出ているのを感じ、こちらまで歓びが伝わってきました。そんな彼女も、ヨーガをする前は仕事のストレスで体調が調わないことがあったようですが、今ではそのようなことはなくなったと話されました。
改めて、ヨーガって本当にすごい!!一人の人の人生を大きく変化させる、なんとすごい力でしょう!!!!是非またこのような機会が持てたらと思います。