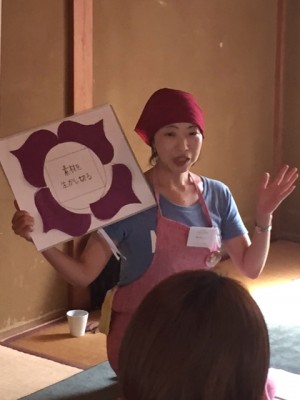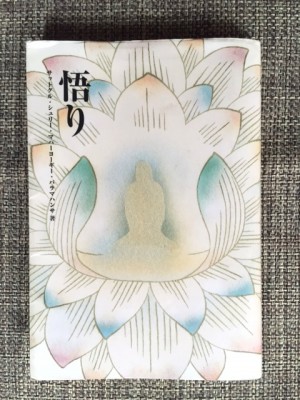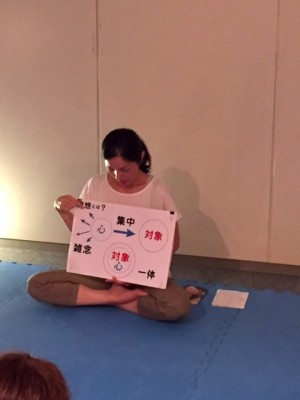ガネーシャ庵には、ガネーシャ神のような風貌の友人が住んでいます。
京町屋の昔ながらの長屋のような建物で、三軒がつながっていて、その真ん中にガネーシャ庵はあります。よくお邪魔してヨーガの話をしたり、打合せに使わせていただいたりしています。
先日、いつもバクティ・サンガムをしているミラバイとガネーシャ庵に伺った時に、少しだけキールタンを歌う機会がありました。
ゆったりとした夕暮れのひと時の中でミラバイが歌うキールタンを聴きながら、ふとずいぶん昔に訪れたエジプトを思い出しました。
夕暮れ、礼拝の時間にイスラムの音楽が朗々と街に流れるのを聴いて、あぁ、こうやって忙しい生活の中でも神への讃歌を耳にすることで心は神に戻されるのだなあと思いました。あるインドの日常の映像の中で、キールタンを歌う素朴な歌声を聴いた時にも同じ印象を持ちました。
本当に日常の中に神があり、神への信仰とともに生きているのだなあという印象です。
次の日、隣の住人の方から、「美しい歌声が聴こえていました〜突然のプレゼントに癒されました」との感想がありました。長屋ならではのプレゼントですね〜 ヾ(=^▽^=)ノ
京町屋の日常の風景の中で、普段着で歌うミラバイのキールタンを聴いていると、心は日常の喧噪から引き戻され、私たち自身の原点である神の下へ駆け寄るような気がしました。ずっと聴いていたいなあと思いました。そして、毎日夕暮れにほんのひと時でもいいから聴きたいと思いました。そうすれば、忙しい生活の中でも、心は神への愛を忘れることはないでしょう。以来、家でもキールタンをよく聴き、歌うようになりました。
来月は、大阪10月2日(金)、京都10月25日(日)にバクティ・サンガムがあるようです。キールタンを学んで、日常の中で歌い、神への愛を思い起こし、心を常に原点にリセットしたいですね。
それでは、ミラバイが弾いてくれたハルモニウムの音色をほんの少しだけお届けします。ハルモニウムって今回初めてじっくり見たのですが、素朴な作りながらもとても綺麗な楽器で、さまざまな音が重なった素敵な音色だと思いました。結構大きな音ですが、すごく瞑想的だなあという印象を持ちました。今回はハルモニウムの音色だけになりますが、ミラバイのキールタンを聴きたい方はぜひバクティ・サンガムに参加してお楽しみくださいね。
..
サーナンダ
「ブログ村」をクリックしていただけると励みになります。